若き将軍で皇女・和宮と結婚したことで知られる14代将軍・徳川家茂。
漫画『青のミブロ』では幼名・菊千代の名で登場します。
家茂の特筆すべき活動としては、家光以来230年ぶりに京都に上洛を果たし、天皇から攘夷実行のプレッシャーを受けつづけたことです。
この記事では、そもそも家茂が京都へ上洛した理由を解説します。
14代将軍・徳川家茂とは?

ペリーの黒船来航以来、混迷を極めた日本。
そんな難しい情勢の中、
13歳という若さで徳川幕府14代将軍に就任した人物が徳川家茂です。
家茂は、激動の幕末期を生き抜き、
朝廷との関係改善に努めましたが、幕府の存続という重責を果たすことができず、
若くして世を去った将軍というのが通説です。
その家茂を象徴する出来事が、文久3年(1863)3月4日の京都上洛です。
徳川将軍としては3代家光以来、230年ぶりの上洛で、
家茂18歳のことでした。
将軍・徳川家茂が230年ぶりに上洛した理由
徳川家茂が230年ぶりに京都へ上洛した理由は、
朝廷からの攘夷実行の督促への返答として、”攘夷の策略”を説明するためでした。
将軍・徳川家茂が上洛するまでの時代の流れ
なぜ、説明のために上洛する必要があったのか、
まずは、家茂が上洛するまでの時代の流れを整理します。
つまり、家茂は公武合体により幕府の権威回復を目指す一方で、
攘夷実行を約束するという自らの首を絞めている状態にありました。

文久2年(1862)11月27日 孝明天皇による攘夷の督促
文久2年(1862)2月11日。
家茂と和宮の婚儀が行われ、公武合体が実現します。
一旦落ち着くかにみえましたが、公武合体派と対立していた尊王攘夷派の勢力が強まり、
「即刻攘夷」の気運が高まりました。
つまり、約束された10年以内という期限など待っていられないという意見です。

そして、文久2年(1862)11月27日。
即刻攘夷を唱える公家の三条実美、姉小路公知の2人が土佐藩などの兵に付き添われ江戸に到着し、
将軍・家茂に勅書を伝達しました。
つまり、攘夷の督促が朝廷より幕府に対して伝えられたのです。
これに対して、将軍家茂より、勅書を受け入れ、攘夷の策略などについて、来年早々上京して申し上げるという返答書が渡されました。
文久3年(1863)3月4日 18歳の徳川家茂の上洛
文久3年(1863)2月13日。
将軍・家茂は老中をはじめ、総勢3,000人を従えて江戸を出発しました。
家茂が入京したのは、約3週間後の3月4日。
3月7日には参内して孝明天皇に謁見しています。
そして、孝明天皇からは長く京都にとどまって、警護にあたることを要請されました。
江戸に帰ることを許されずに、攘夷の督促を受けつづけた家茂は、
ついに5月10日を攘夷決行日と回答し、約束させられます。
幕府にはその意思がないにもかかわらず、
攘夷を拒否することができない状況にどんどん追いやられてしまうのです。
このような人質同然の状態がつづき、6月にやっと退京することが許されました。
将軍・徳川家茂の初上洛のその後
攘夷実行を約束した家茂ですが、
その意思に反して長州藩が攘夷を実行しました。
文久3年(1863)5月10日、偶然にも下関を通過したアメリカ商船を砲撃。
つづけてフランスとオランダの軍艦も砲撃します。
しかし、結局はアメリカとフランスの軍艦に砲撃を受けて敗北に終わりました。
それでも、この長州藩の攘夷実行に対して、孝明天皇は6月1日に「皇国の武威を海外に輝かすべし」と称賛しており、朝廷内で過激な尊王攘夷派の勢力が絶対的な地位を占めます。
その勢いは孝明天皇のコントロールができないほどでした。
・朕存意は少しも貫徹せず
・予好まず候えども、とても申し条立たざる故、この上はふんふんという外致し方これ無く候
『孝明天皇紀』
意見がまったく通らず、ただ「ふんふん」とうなずくことしかできないと孝明天皇は嘆いていたのです。
そこで、文久3年(1863)8月18日に長州藩とそれに加担する過激派の公家を一掃するクーデターをおこしました。
いわゆる8月18日の政変です。
政変を受けて、再度家茂が上洛し、諸大名や有志と話し合って国の新しい方針を確立することを求める声が高まりました。
江戸幕閣の反対で上洛が遅延したものの、元治元年(1864)正月に2度目の上洛が実現します。
そして、元治元年(1864)4月29日に家茂は参内し、横浜鎖港を命じる聖慮への請書を提出しました。
つづいて、慶応元年(1865)5月16日には第二次長州征伐に向けて家茂が江戸を出発し、閏5月22日に3度目の上洛をしました。
しかし、翌慶応2年(1866)正月に薩長同盟が結ばれ、6月に第二次長州征伐が開戦となりますが、幕府は劣勢。
そして、戦争の最中、慶応2年(1866)7月20日に将軍家茂は大坂城で死亡してしまいました。
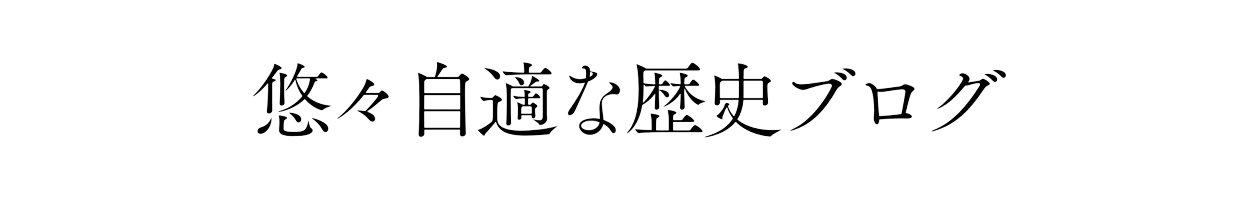




コメント